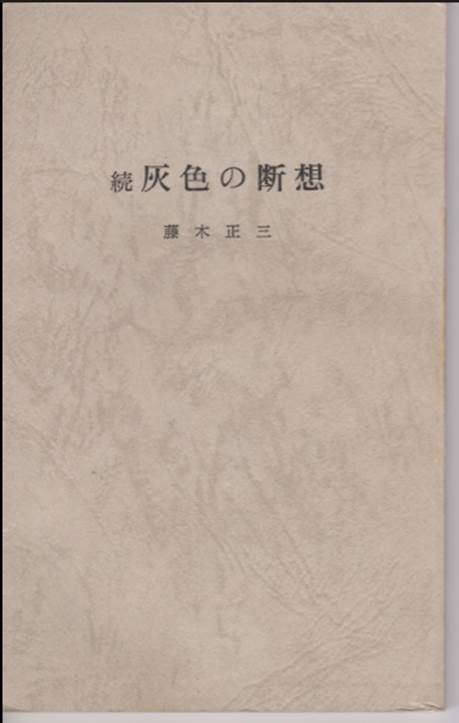
|
誠実、無欲、色でいえば真白な人、不実、貪欲、色でいえば 真黒な人、そんな人はいずれも現実にはいません。いるのは、 そのどちらでもない灰色の人でありましょう。比較的白っぽい 灰色から、比較的黒っぽいのまでさまざまではありますが、と にかく人間は、灰色において一色であります。その色分は一人 の人間においても一定ではなく、白と黒との間をゆれ動いてい るのであり、白といい、黒といっても、ゆれ動いている者同志 の分別に過ぎません。よくみればやはりお互いに灰色でありま す。灰色は、明るくはありませんが暖かい色です。人生の色と いうべきでありましょう。 |
|
|
目 次 |
|
|
端的に 美的に |
|
|
幸福でなければ生甲斐がないかのように言います。しかし、人生 は幸福である筈だと考えるのは一体何を根拠にしてのことなのでし ょう。人生が本来不幸なものであったとしても、別におかしくない ではありませんか。人生は幸不幸に何の関係もない、生きるという 単純な事実だからです。この単純さに幸福とか生甲斐とかやたらに 価値づけをしたがるのは、迷いであります。日々果すべきことを精 一杯果して、それで満足して生きている人の単純さを軽蔑してはな りません。そこには事実に徹して人生を見た人の眼光があります。 社会のため、平和のため、正義のため、確かにそういうことのた めに人は生きるべきです。しかし、ためにためにとあまりいわれる と、怠けるわけではありませんが、いささか嫌気が差してくるので はないでしょうか。この嫌気を、なにか利己的な怠慢のように思い がちですが、これこそ観念の世界から私達を解放してくれるものな のです。愛、正義、誠実などの観念は、動物とちがって人間が持つ ものですが、時にはそれらに嫌気を差すことが必要です。私達は、 そういう観念であまりに上ずった生き方をしているではありません 辺境の地は、その差別の故に抵抗の論理を生むといいます。しか し、差別されて金にも名誉にも権力にも縁のない人には、そういう ものに意味や目的を置いている人に見られない、実直で暖かい人が 多いものです。人間として精一杯生きること自体に満足できる、い はば、人生の職人のような人がいます。見方によれば、諦念かもし れませんが、透き通ったような人がいます。辺境の地が抵抗の論理 を生むとだけ考えるのは、人間のあさはかでしょう。そこは、意味 も目的も越えて、人生に端的に人間がなれる、信仰の論理が生まれ るところでもあるのです。 何人の口もさしはさむことを許さない尊厳が、良心にはあるとい われます。いかなる権威の介入も許さない自由が、良心にはあると いわれます。しかし、良心というものは、人生に対する恐縮であり ます。生きること自体にとがめを覚えているような、晴れない心な のです。ですから、良心の自由と尊厳は、疑惑も恥じらいもなく、 主張すべきものではありません。他人の視点を無視して黙々専心、 自分を悲しみ得ることにおいて、良心は自由であり尊厳であるので す。この悲しみのない堂々たる良心、人間の虚栄の極みであります。 相手の身になって、と簡単にいいますが、その積りでしたことが、 相手の重荷になっている場合も少くなく、難かしいものであります。 むしろ、自分を控えることが持つ意味を、大切にしたいと思います。 自分を控えるとは、無関心のことではありません。相手の姿の中に、 自分と同じ弱さを見て、物が言えないということであります。この 共感、この沈黙、それが人間関係に節度を与えるでありましょう。 そして、人と人とを結びつけるのは、あれこれをなすよりは、この 節度である場合が、かえって、多いものであります。 神はあるのか無いのか、この問いが人間の魂の最も深い呻きで あるといわれます。そして宗教はこれに答えるものと考えられます。 しかし、果してそうなのでしょうか。この問を発せしめているもの に注目しましょう。さまざまな執着に翻弄される、霊肉葛藤の事実 が私たちになければ、この問は出て来ないでありましょう。宗教は、 まさにこの僕悩の事実に答えようとするものなのです。神の存在の 有無を、第一義的に問題にしているものではありません。僕悩直視、 それが宗教であります。神はなくとも宗教はあるのです。 宗教は政治に対して距離をもたねばなりません。それは、現実の 問題に無感心だからでも、逃避するからでもありません。たヾ一点 「共に是れ凡夫」を自覚するからであります。政治には「共に是れ 凡夫」という視点はありません。あっては政治にはならないのです。 そこにあるのは、抗争する力であり、対立する利害であり、従って、 相手に対する仮借なき追究の視点こそ、求められるからであります。 それに対して、「共に是れ凡夫」を、人間の事実を端的に主張して 止まないものと考え、自らの視点として選ぶのが宗教であります。 ねたみとは、たとえば、人の幸せを喜べず何らかの理由をつけて 相手を過小評価しようとする、そういう気持ですから、そこでは事 実を事実として認める素直さが欠けています。ですから、ねたみが 持っている最大の問題は、ねたんでいる相手に対する問題ではなく て、ねたみによって否定されている事実に対する問題なのです。頭 を下げるべきものに、謙虚に頭を下げていないという、真理に対す る問題なのです。ねたみによって拒否されているのは、人ではなく て真理なのです。ねたみの持つおそろしさはここにあります。 どんなことでも落着いて考えて見れば、よってきたるところはま ずわかるものですが、どう考えても説明がつかない、結局はものの はずみというより他ない場合もあります。歯が痛いとか、澄みきっ た青空を仰いだとか、なんでもないことで変わってしまうようなた わいなさが、人にはあります。もちろん、そんなことがしばしばあ るものではありませんし、またあっては困りますが、それでも、も ののはずみが果たす役割は、私たちが思っているよりは、遥かに大 きいものです。この辺がわかると人間優しくなるものです。 誤りを犯したら、そしてそれが取り返しのつかないものなら、と に角人生を止めるわけにはゆかないのですから、頭を下げて進ませ てもらいましょう。人生は、誤りの連続であり、また一人で生きて いるわけではないのですから、誤りを犯したからといって、いちい ち立ち止まるのは、良心的に見えて偏屈で、独善です。勿論、誤る のは当然であると頭を下げないのは、人生に対する不遜として論外 です。お互い頭を下げ合って進んで行く平凡に、人生の本来あるべ き実際の姿があるのです。素直で純粋な心には、それがよくわかり ます。 愛することはむずかしいといわれます。しかしそれ以上にむずか しいのは、愛されていることに気づくことです。愛がこの世に無い わけではありません。どれだけ多くの人の好意と配慮に支えられて いることでしょう。しかしそれに気づくには、私たちの心はあまり に自分本意に固まり過ぎています。だから愛は、人を愛するより前 に、人に愛されている自分に気づく反省の問題として、先ず出発せ ねばなりません。この反省に裏付けられない時、自己満足の偽善に 陥るか、挫折して絶望に陥るか、いづれにしても愛は退廃を免れま せん。 失敗を繰り返しながら、人は生きてゆくものであります。そして、 そのたびに、それをかくそうと構えたり、逆に他にほこ先を向けた り、人の評価を気にして自己嫌悪に陥ったり、心は騒ぎます。その ように騒いでいる心は、失敗を直視する能力を失っています上に、 失敗を正当化しようとする卑怯さが育つ土壌でもありますから、失 敗した場合の喫緊事は、すみやかにそれを収拾することではなく て、心のこの騒ぎを鎮めることであります。その際、最も有効な道 は、自分を、そして自分だけを、俎上にのせることであります。 私どもは色々な経験をしますが、そのことごとくをしっかり受け とめているわけではなく、大半は傍に置き去りにしながら生きてい るようです。それに、その受けとめ方も、関心の持ち方次第で随分 偏っているわけで、受けとめる力の方も、人によりさまざまでしょう が、いずれにしても受けとめ切るはずはなく、丁寧に生きているつ もりで、お互い無造作な偏った生き方をしているものです。偏ること なく生きるなど、望むべくもありません。偏向というと特別のこと のように思いますが、人間にとって、それはその卑小を示す一つの 常態なのです。 勤勉とは、休む間もなく務めることではありません。まっすぐに 生きるとは、一度心に定めたことを貫きとおすことではありません。 すべきことをしないで、したいことを忙しくしているのは、怠慢で あるし、改めるべきことを改めないで、自説を固守しているのは、 曲がった生き方といわねばなりません。怠慢な勤勉もあれば、曲が ったまっすぐもあるのです。要は心の一番奥のところで、自分をす てているかどうかの問題です。この「すてる」問題を最大の、そし て生涯の課題として生きる、それが醒めた人間の生活というもので しょう。 私たちが抱く願いには、どうしても欲や自惚がまといつきますか ら、成就することが、かえって身を滅ぼすに至るような場合もある わけで、やはりそういう願いは、願いというよりは欲であると自覚 して、はっきりそういうべきであります。案外私たちは、自己執着 を願いと錯覚しているだけで、一度も、願いというにふさわしい願 いを持ったことがないのかもしれません。人が持つべき、そしてお そらくその名に値する唯一の願いは、執着から自由になること、で ありましょう。願いという言葉を、もう少し慎重に使いたいもので あります。 堕落とは、欲に流されて低俗に落ちてゆくことを、必ずしも意味 しはしません。欲を抑えて倫理的に高まってゆく努力の中にも、堕 落の危険性はあるのです。至りついたその高さを意識した時、高く なる努力は、直ちに偽善であり、そこで人は落ちるからです。高く なるとは、本来自分の至りついた高さへの意識を失ってゆくことで あるはずであります。堕落は、高い低いの問題ではなく、至りつい た高さを測定したがる、位置についての意識過剰の問題であります。 禁欲主義とは、その意味で、崇高な堕落といえましょう。 誤解されると弁明したくなります。批判されると反論したくなり ます。もちろんそうすることがヽ議論を徹底してゆくために、必要 な場合もあります。しかし、弁明にせよ、反論にせよ、真理を主張 しているつもりで、いつの周にか、組手に自分を認めさせるだけの 低い努力に変わってしまうことがよくあるのです。ですから、むし ろ弁明や反論を、ほどほどにおさめる頃合こそ大切であります。徹 底的に議論することが、必ずしも真理を徹底的に論じているとは限 らないのです。徹底した議論はヽ時に空虚ですらあるのです。 先の先までは無理としても、たしかにある程度人生は見通せます から、自分で何か事を企て行動に移すことは無謀ではなく、むしろ 当然のことですが、一方、解答を見出し得ないままに、とにかく進 んでゆかなければならぬような問題もあるわけで、人生が見通しの よいものでないことも、承知しておかねばなりません。事が順調に 進んでいる時でも、問題を置き去りにして先を急いでいる後ろめた さを抱かざるを得ないようなところが人生にはあります。置き去り にした問題の累累たるさまの見えない人は人生を語る資格を持ちま せん。 物質的豊かさがもたらす先が見える時代になりました。内面的力 の衰弱が指摘され、心の豊かさが求められています。しかし、問題 は物から心へ方向転換することで片付くものとは思われません。そ こには依然として功利主義が支配しているからです。功利主義とは、 人間の限界に対する無知と、人間の課題を抹殺する怠慢と、人間の 構造を無視する傲慢において成立つ自己神化・反逆なのです。現代 の病根は、心の状態を衰弱ととらえて、反逆ととらえ得ないところ にあるのです。反逆している相手が見えないところにあるのです。 どんなに正しい主張も、それが持続しない限り、正しいと呼んで はなりません。時の経過と共に現われてくるさまざまな角度からの 光の照射に耐えて、主張し続け得るものでなければ、正しいと呼ん ではなりません。持続性は、健全な妥当性を保証する正しさの属性 だからです。持続しない正しさは、一時的で無責任な自己満足に他 なりません。私たちはこの自己満足をも、その瞬間的な鋭さの故に、 正しいと呼び勝ちです。しかし、続かないものは正しくないのです。 そう断定しきってはばからない重厚さが、人生にはあります。 人生は厚味のあるものだと思います。だからこそ、色々な矛盾が あるのでしょう。矛盾は、人生に厚さのあることを教え、また人生 を見抜く目を養ってくれます。ですから、本質的にそれは、甘受す るところに意味があるものなのです。勿論、それを克服してゆくこ とは必要です。しかし、単に克服すべきものとしかそれを見ないの は、人生を皮相において見る軽薄です。矛盾に甘んじる態度を、よ く人は奴隷の所業のようにいいますが、そうではありません。それ は、人生への明晰なのです。矛盾を甘受する人、人生の貴族であり ます。 避けられるものなら苦労は避けて暮せばよいと思いますが、人を 愛する苦労だけは避けますまい。いろいろな姿をとって現われてく る人生も、結局は、お互いいやな思いをさせたりさせられたりして、 もつれているところにその一番深い姿があるわけですから、愛する 苦労を避けていては、人生の本当の姿はわからないでしょう。人生 は苦労しなければわからないと言いますが、苦労が人生修業に意味 を持つのは、この愛する苦労でそれらが貫かれている時だけで、そ うでなければ、どんな苦労もただの苦労にしか過ぎません。 人生の真実を求めて深刻に悩んでいる人が、一寸した慰めの言葉 などで簡単に元気を取り戻すのを見ると、案外だなあと思いますが、 人間の深刻さとは、所詮その程度のものなのでしょう。深刻なこと を言っているようで、実は同情を求めて物欲しげであったり、野望 を企んでたくましくあったり、という場合が多いもので、結局、深 刻とは浅さをごま化す偽装であります。人間の深さというものは、 自分に破れ果てた心貧しい人のものでありましょうから、深さにふ さわしい装いは、深刻よりはむしろ微笑であるはずであります。 不正と戦い続ければ、いつかは正しい社会が来るかといえば、お そらく来ないでしょう。それに、そんなことはあまり考える必要は ありません。何故なら、正しい社会の到来が期待され得るから不正 と戦うのではなく、不正を許してはいけないから、ただそれだけの 理由で不正と戦うべきだからです。結果を考えた上で、不正への態 度を定めるのは、正しいことではありません。正しく生きようとす る者は、報いられなくてもよいと心定めて、無名碑を刻めばよいの です。無名碑とは、永遠を信じる美しい満足であります。 人の幸せのために生きるのが、高くて良い生き方であり、自分の 幸せのために生きるのは、低くて悪いことのようにいいます。しか し、高く生きているつもりで、その上調子の使命感には閉口させら れる、ということも少なくないわけで、むしろ、自分の幸せを一生 懸命求めている人の方が、正直で嫌みがなく、気持ちがよろしい。 お互い平凡な人間なのですから、高いとか低いとかよりも、せめて 人に嫌な思いをさせないよう、心がけて生きたいものです。嫌みが ないということは、人に対する最低限の礼であり、愛でありましょ う。 社会のためにどれだけ役立つか、その有用性ではかるには、信仰 はあまりに深く永遠にふれています。幻のような神秘的体験の有無 ではかるには、信仰はあまりに人格的であり、首尾一貫した思想と するには、信仰はあまりに鋭く人間の虚無を見ています。信仰団体 の組織維持の努力に価値を認めるには、信仰はあまりに無形であり、 結婚式や葬式のような社会的習慣とみなすには、信仰はあまりに生 命的でありましょう。信仰とは、結局美的生活であります。自分を 残すまいとする意志に美しさを感じる、美的生活であります。 何らかの意味で人間を超えたものに触れたところに成立つのが、 信仰です。だから超えたものに心を開いてこそ信仰ですのに、ともす れば超えたものよりも、超えたものに触れている信仰自体を大切に し、小さい自得の世界をつくりあげる誤りを犯しやすいものです。 しかし、信仰は如何に純粋かつ祈念に満ちたものであっても、超え たものが人間に触れた跡であり、それは、やがて変化し、結局は何 もなかったかのように消えてゆくに過ぎません。そう「自分の信仰 を軽んじ得ること」が、実は信仰でありましょう。 信仰は幻想に過ぎないと批判されます。しかし、幻想か否かで信 仰をきめてはなりません。人の心を自由にし、雄々しく思いやり深 く生かしめるものなら、たといそれが幻想であってもよいではあり ませんか。そういう信仰なら、幻想として斥けるよりは、人生への真 剣さとして評価すべきであります。大体、それぞれに人生を解釈し、 夢を画いて生き、いささかの諦めをもって閉じてゆくのが人生で、 結局、皆幻想を生きているようなものではありませんか。信仰も、 数ある幻想の中で許された、美しい一つかもしれません。 私たちは、何らかの意味で葛藤を味わいながら生きているもので あります。そして、それをいつかは克服できるものと考え、その願 いを信仰に托し勝ちであります。しかし、信仰は葛藤に終止符を打 つものなのでしょうか。むしろそれは、低きについて葛藤から安易 に脱れようとするものに、高きを思わしめ、葛藤へと招くもののよ うであります。所詮は葛藤に他ならぬ人生に毅然と直面せしめるも ののようであります。それは、葛藤を斥けずに、微笑をもって受け 入れる余裕の、静かに湧き出してくる泉のようなものであります。 心のどこかに不透明を感じたならば、そのよって来たるところを 求め、改めるべきは素直に改めて、透明になるように心を整理しま しょう。私どもの心は、不透明さにすぐに慣れ、それが放置されて 加速度的に増して来ても、何とも感じなくなるのです。面倒ですが 手を抜かずに、いちいち整理作業をしてゆきたいものです。そんな ことをしなくても、別に生きるに差しさわるわけでもなく、むしろ、 そのような心の労働は、人を生き難くさえしますけれども、それで も、人を偽善から守るのは、この心の労働以外にないのです。 信仰生活には人間の自然な気持を押えるような面があります。信 仰者には別の生活基準があるわけですから、そういう無理に耐える ことは義務でもあり使命でもあります。しかし、それを義務とか使 命とか深刻に考えている限り、信仰は未熟というべきでしょう。山 の上にある町が隠れることのできないように、本来それは信仰の自 然な姿なのですから。何事でもそうでしょうが信仰においても自然 であることがその錬達を示します。深刻に気負った理想主義を自分 の信仰に見出したならば、人はその未熟さを反省すべきです。 真の宗教は、喜びを現実に与えるものでなくてはならない、とい われます。しかし、これは宗教を測る尺度としては、あまりにも人 間の分別から割り出されたものではないでしょうか。宗教が真理の 啓示であるとするなら、決定的に非真理である人間にとって、それ は何よりも反省を迫る圧力であり、その圧力の下で味わうのは喜び よりも先ず苦しみでありましょう。宗教が、もし喜びを直接的に与 えるならば、それはそれが非宗教であることを示す以外の何もので もないのです。とにかく測る分別でなく、測られる虚心が、そこで は大切であります。 信仰には、理解を積み上げて追究してゆくのではなくて、そうい う追究を省略して、不分明な点を残したまま飛躍して決断してしま う面があります。この省略の決断の故に、信仰は逃避とか、幻想と か、欺瞞とかいわれます。否定できない点もあります。しかし、実は この省略の決断は、追究の努力の放棄ではなくて、人間の限界への 節度なのです。人はこの決断において、知識や経験や道徳や、その 他なにか人間的なものに基づいて神を知ろうとする傲慢から身を守 っているのです。信仰とは、限界に開眼した人間の節度を示すもの でしよう。 現実の世界における無力な状態を、永遠の世界を思ってあきらめ る、ということがあります。しかし、現実の世界で有力であること が、永遠に対する感覚を鈍磨さすことをおそれ、永遠の世界を生き ることこそ人生の一大事と考えて、あえて無力な状態を選びとると いうこともあるのです。そして、無力が担っている永遠を、生きよ うとすることがあるのです。無力とは、現実の矛盾を担っている永 遠の姿であり、有力とは、永遠を忘却している現実の姿なのです。 無力をあえて選びとる、ここに永遠を生きようとする者の祈があり ます。 誠実、柔和、謙遜、慈悲など、美徳にはちがいありませんが、所 詮は人間のすることですから、自惚や自己満足のようなものが必ず ひそんでいると考えるべきでありましょう。ですから、そのひそん でいるものへの反省がなされている限り、それらは美徳なのであっ て、反省なしにそのままに主張されるならば、美徳はいつの間にか 傲慢をはらんでくるでしょう。罪は堕落の相において現れてくると は限らないのです。美徳の相のもとに現れてくることもあるのです。 美とは本来、「主張をしない姿勢」に伴うものであります。 衣食足りて礼節を知る、といわれます。衣食が足りないと礼節を 欠いてしまう人間の弱さは否定できません。しかし、足りたところ でなされる礼節とは一体何なのでしょう。礼儀とか節度とかいうも のは、本来、衣食が足りなくてその為に人間関係が汚れてゆく時に、 それに抵抗するところに真骨頂を発揮するものではありませんか。 それは、品位の崩れから身を守ろうとする抵抗の問題として、人に 対するよりは、先ず自分自身に対する姿勢として理解されねばなり ません。礼は先ず自分自身に対する礼でなければ無礼であります。 いやなことをされると、腹を立て仕返しをしてやろうと思います。 立場が逆になると、相手も同じことを考えるでしょう。人間の生活 というものは、たしかに、報い合いながら展開してゆくものであり ます。しかし、だからといって、報い合いの構造から脱しようとも せず、その循環の中を生きることを当然とするのは、人生をみずか ら卑しめることでありましょう。むしろ、報い合いの構造から離れ て、相手の気持に支配されず、自分自身の感情に流されない、自由 な立場を求めて生きて、人生を祝福したいものであります。 私たちは、思い通りに生活がゆかなくて何かしら不満をたえず抱 き、またあくせくと自分のことばかり求めて、そのために生活を実 際以上に重いものにしているきらいがあります。そういう生活を、 本来あるべき重さに軽くしてくれるのが信仰というものです。信仰 は、日常生活からの隔たりによって、生活へのとらわれを除き、広 い境地に導き出してくれます。そして、不満にゆがむ心に自ら足る ことを教え、あくせく求める心に人を顧みる余裕を与えてくれます。 自足と愛は、信仰の教えてくれる人生本来の重さであります。 何ものをも加えず差引かず、教えられるままに受容するのが、信 仰において正しいことのようにいわれます。しかし、教えられると ころに反発したり、自分の考えを主張したり、とつおいつするのは 当然なことで、それを押し殺してしまうのが正しいこととは、思わ れません。むしろ、納得するものを自分なりに掴んでゆくいとなみ こそ、大切ではないでしょうか。信仰の受容とは、自分を押し殺すこ とではなくて、とつおいつする自分を息長く正直に見続ける真実な 執念、そこにおいて起こる一つの生涯かけての事件であります。 宗教は社会の矛盾をおおいかくす阿片であると批判されてきまし た。否定できません。しかし、宗教は本来自分を深く見る眼を与える ものですから、それは罪の自覚を促し、遂には人間的な一切を、所 詮は空しい狂奔とみなす永遠なる視点を与えるでありましょう。こ のような視点から社会を相対的なものに過ぎないと軽くみなすこと を阿片と批判されるのであるなら、それに甘んじるのが宗教の負う べき十字架であります。他の一切を忘れるほどに深く罪に開眼して いることは、決して恥ずべきことではありません。 信仰とは、ひと言でいえば、前進ではなくて後退のことなのです。 神を目的として求めてゆくことではなくて、神の目的となって問わ れて退いてゆくことこそ、信仰の本質なのです。問われて現状に留 まることができず、どうなるかもわからないままに、とにかく変わ ってゆくより他ない、ということなのです。アブラハムが、行く先 を知らないままに出ていったようにです。信仰は、生の目的を示し て、それへと導いてゆくようなものではありません。それは、今あ るところを常に問い、突き崩して、安住を許さないものなのです。 祈ったところで現実は少しも変らないではないか、それよりは具 体的行動を起こすことこそ祈りではないか、とよく批判されます。 しかし、これは祈りに対する誤解であります。祈りは問題解決の手 段ではなく、問題の渦中で自分が失われないように自分を守ること なのです。具体的に効果があるか否かという観点だけで現実の諸問 題に直線的に対応していると、人は平板に拡散してゆくものです。 この拡散に抗して、人間として自分を守る凝縮作用が祈りでありま す。祈りは問題解決の手段ではなく、実はその前提であるのです。 神について語るということは、物や人について語るのとは自らわ けが違うのですから、やはり、自分の弱さとか限界とかが見えて来 た時でないと、真実には語れないように思います。しかし、それが 見えて来た時は、神について語ることが傲慢であることに気がつい た時でもありますから、結局、神について語るということは、人が 久しく抱いて来た大きな錯覚ということになりましょう。それはゆ るされないことでした。人は自らの卑小と相対性を自覚して、ただ 生きていればよいのです。神を語るに、この生活に勝る言葉はあり ません。 自然法測に合致しない精神現象を霊の働きと考え、死者との交霊 や虫の知らせのような不思議な現象があると、それを霊的現象とい う人もいますが、霊の働きはそのような超自然性にあるのではなく、 真相を顕わにする明察性にあると思われます。時には審き、時には 醒まし、一時には鎮めながら、人の心の真相を明らかにして偽りなか らしめるのが、霊であります。ですから、その明察に対しては、罪 の自覚で応えるよりほかに、人は霊に対する道はないのです。自分 の罪に真実に泣く、これほど霊的な現象がありましょうか。 皆が善意をもって誠実に交わっているのに、いつの間にかそれが 争の原因になっている時があります。正義を愛し不正を憎み理想を 求めている努力が、いつのまにか人をさばく傲慢になっている場合 もあります。こういう変質を起こさせる人格的損壊ともいうべきも のが、人の心の内深くあるようです。私たちが常に相対的なものと して目ざめていなくてはならないのは、単にその生命に限界があ り、その能力に限界があるからではなく、この損壊のためなのです。 相対性とは、人格的損壊の懸念に促されて自覚されるものです。 人は何によって一つになるのでしょう。一つの目標を目指すこと においてでしょうか。思想や信仰を同じくすることにおいてでしょ うか。そういうことで一体感を味わう人もあります。しかし、そこに は人間への誤解があるように思います。人は、共通のものに関わる ことによって一つになるように見えて、実は、共通の事実を内に自 覚するまでは、一つにはなれないものではないでしょうか。そして、 おそらく罪をおいて他に、その共通の事実に出会いえないでありま しょう。罪において一つ、一体感に内容を与えるのは、これです。 神を求めれば求めるほど自分を省みずにはおれなくなり、自分を 省みればみるほど神を求めずにはおれなくなる、神を愛しようとす ればするほど隣人を愛することが課題となり、隣人を愛しようとす ればするほど神への愛が問われてくる、神と共に生きようと願えば 願うほど日常生活が重大になり、日常生活を大切にしょうとすれば するほど神と共に生きることを願わずにはおれなくなる。具体的な 人生とは、この循環を生きることでありましょう。片方を切り捨て た神の無い生活も、生活のない信仰も、共に抽象的であります。 自分の意見ややり方が、どんなに正しいと思えても、絶対的には 正しいと思わず、むしろ間違っているのでないかと反省する。つま り、自分を軽く見てゆく。自分の意見ややり方が、どんなに一般的 には認められなくても、自信を失わず、そうでしかありえない自分を 大切にする。つまり、自分を重く見てゆく。信仰とは、この二つの 見方で、自分を見つめる複眼を与えてくれるものでありましょう。 なぜなら、神は人間が絶対者たることをゆるしたまわないと共に、 人間が落後者たることにも耐え得たまわないからであります。 お互い何事かを確信し、いろいろなことを主張し、行動してはい ますが、さてそれらがはたしてどれだけの妥当性をもっているのや ら、考えてみれば心もとないことです。生きることを止めるわけに もゆかず、間違いだらけのままにとにかく私共は生きているわけで す。結局は何一つわかっていないのでしょう。しかし、一つ言える 確かなことがあります。わからないなりにも思いやり深く生きてい ると、人生というものはなんとか恰好がついてくるものだというこ とです。愛が全ての間違いをおおってくれるからでしょう。 イエスの十字架は、二人の犯罪人の十字架と共に立ちました。そ の一人は、悔改めて救の言葉を死の間際に賜わりました。もう一人 は、罪を告白せずそのまま死にました。これは、悔改めるものは救 われ、そうでないものは滅びることを示しているのでしょうか。い いえ、十字架の側では、悔改めるも、悔改めざるも同じであること を示しているのです。悔改めるか否かで、人間の運命がきまるかの ようにいう、宗教的おどしに注意しましょう。人間の悔改めなどし れているのです。十字架が私の側に立っている、それで全てなので す。 著者について 林 忠良 先に発行された正篇に著者紹介があるので、少し角度をかえて一二誌してみたい。先生の立場は大学時代以来の新約聖書研究と、デンマークに留学されてのキルケゴール研究とに裏附けられている。しかし先生の口からキルケゴールのことが直接語られたのを聞いたことはついぞない。それは先生が、いろいろな思想を理論的な興味で論ずることよりも、寧ろ、生死に生きる一人の人間として、その自己の身上において問題を把え取組もうとされる結果であろう。その先生のあり方は、古来の「学道」に連なるものであるように思われる。生死に生きる人間にかかわり得るものは、もってまわった議論ではなく、「端的」なものでなければならない。しかもそれは抽象的、観念的なものではなくて、美しいものを美しいとみる日常の具体的な生の底にまでとどいているものでなければならない。かくして生まれる先生の端的にして美的な断想は、こういう先生の思想的宗教的格闘を籠めた奥行を秘めている。キルケゴールの講話が、聖書の字義を離れつつも、かえってその使信の核心に切込んで行くように、こうして生まれ書かれた先生の断想が、一見端的にして美的でありながら、かえって問題の核心、聖書の使信の核心を射当てる訳はそこにある。それ が先生の狙いでもあろう。 (教会役員、関西学院大学経済学部助教授) この小冊子は、昨年クリスマスに出版された「断想」の続篇です。内容は、先の正篇と同じく、当教会の週報に掲載された断想を、集めたものです。これらの断想は、若干の例外はありますが、できるだけキリスト教用語や表現を避けてまとめられた、前週の礼拝説教の要旨です。しかし、見方をかえれば、著者の真実を生きようとする、求道の途上に産み出された思想とも言えましょう。これが、教会の内外の別なく多くの共感を得、続篇を待つ声の寄せられた所以と、思われます。 昨年の発行に際し推進役を果たされた熊谷哲夫役員は、現在療養中ですが、第二輯の実現についても熱心に勧められました。同氏の病床よりの促しに応えて、本続篇は、ここに発行されることになったのです。 この小冊子が、ふと立止って人生を考えるきっかけともなれば、と願っています。 (教会役員会) 注; 1.
このページでは1973年教会発行の初版本「続灰色の断層」の雰囲気を保つよう努めました。なお、掲載に当たり藤木牧師のご子孫の了解を得ております。 2.
上記の「続 灰色の断想」の原稿は京都御幸町教会が発行した最初の版のものであり、読み上げは後日少々の文言の変更がなされたヨルダン社版のものです。その為、文字表記と読み上げは一部異なる場合があります。 |
|